
風がまだ冷たい。
春の気配は少しずつ近づいてきているはずなのに、海辺を走ると、冬の名残が肌を刺すように吹きつけてくる。
それでも朝の海には、いつものようにポツポツと釣り人の姿があった。
防寒着を着込んで、じっと波を見つめながら竿を握っている。誰も声を出さず、ただそれぞれの釣りと向き合っているようだった。
車の窓を少し開けると、潮の匂いがふわりと入り込んだ。
「そろそろ、水温も少しは上がってきたかな」
とはいえ、まだ浅場に魚が入ってくるには早い気がする。今日のような日は、やはり深めのポイントを探るのが良さそうだ。
そう思いながら、海岸線をゆっくり走る。
風裏になる地形を探しながら、テトラが積まれた場所を見つけると、車を止めた。
潮はそれほど強くない。波も穏やかで、立ち込む必要もなさそうだ。何より、ここなら深さもあって、根魚が潜んでいる可能性が高い。
ゆっくりと支度を整える。
今日はシンプルに、ブラクリ仕掛けにオキアミをつけての釣り。狙うのは、テトラの隙間に潜む根魚たち。
仕掛けを静かに落とす。
スルスルと沈んでいき、オキアミが暗い海中に溶けていくのを感じる。
……反応はない。
潮が動いていないせいか、エサ取りも来ない。
テトラの隙間を変え、落とす場所を少しずつずらしながら、丁寧に探っていく。
数分が経過した頃。
コツ……。
わずかに、竿先がピクリと動いた。
神経を研ぎ澄ませ、しばらく待つ。すると、次の瞬間──
ググッ!
竿先がぐっと下に引き込まれる。反射的にアワセを入れると、ずしりとした重みが伝わってきた。
「……きた」
根に潜られないよう、強めに巻き上げる。
それほど暴れないが、しっかりとした抵抗感。この鈍い引きは、たぶん──
海面に浮かび上がったのは、黒っぽい魚体。
目が大きく、どこか鋭い雰囲気を漂わせたその姿。
「ムラソイだ」
なかなかのサイズ。20cmは超えている。
厚みのある体に、がっしりとしたヒレ。テトラの中でじっと息を潜めていた獣が、ついに飛び出してきた。
「いいね。これは嬉しい一匹」
針を丁寧に外し、バケツの中にそっと入れる。
茶色がかった魚体が、日の光を受けてきらりと光った。
仕掛けを打ち直す。
潮の動きに合わせて落とし方を微調整しながら、再びテトラの影を狙う。
すると、またすぐにアタリがきた。
今度はもう少し軽めの引き。だが、しっかりとしたトルクを感じる。
上がってきたのは──
「カサゴ、やっぱりいたか」
ムラソイほどのサイズではないが、ぷっくりとした体形で美味しそうな個体。
このあともう一匹、同じくらいのカサゴが続けて釣れた。
バケツの中で、ムラソイとカサゴが静かに泳いでいる。
海の色をそのまま映したような魚たち。ゆっくりと呼吸をするその姿を見て、ふと気が緩む。
「これだけ釣れれば、もう充分だな」
冷たい風の中、じんわりと手が温まっていくような気がした。
さて、次はこの魚たちを、どうやって一番美味しく食べようか。
家に戻り、キッチンに魚を並べる。
ムラソイ一匹、カサゴが二匹。どれも身がしっかりしていて、見るからにうまそうだ。
「今日は……全部、あれでいこう」
迷いはなかった。
この魚たちは、あの調理法がいちばん似合う。アルミホイルに包んで、塩とバターでじっくり焼き上げる──それだけで、素材の味が最大限に引き出される。
まずは下処理から。
まな板にムラソイを置き、包丁の背でザッザッと鱗を落としていく。思ったよりも硬く、骨ばった手応え。鱗が弾け、キッチンに軽く散る。
エラと内臓を取り除くと、ぷりっとした白身が現れる。
腹の中には、うっすらと脂ののった身がたっぷり詰まっていた。
同じくカサゴも捌いていく。こちらは少し柔らかく、手慣れた動きで処理が進む。
下処理を終えた魚たちをキッチンペーパーで丁寧に拭き取り、塩をまぶす。
全体にまんべんなく、そしてお腹の中にもしっかりと。バターの香りと塩気が馴染むように、数分だけ置いてなじませる。
「よし、包もうか」
アルミホイルを広げ、その中心に魚を一尾ずつ乗せる。
その上から、厚めに切ったバターを乗せ、香り付けに薄くスライスしたにんにくを一枚。少しだけ白ワインを垂らし、そっとホイルを閉じる。
包みを三つ、グリルに並べると、静かな音が立ち始めた。
ジュウ……
バターが溶け出し、魚の身から染み出した脂と合わさって、ホイルの中でぐつぐつと踊る。
鼻をくすぐるのは、焦げかけたバターの香ばしさ。そしてほんのりと漂う磯の香り。
「うわ、もう絶対うまいやつ」
グリルの扉越しに立ち上る湯気を眺めながら、思わずにやけてしまう。
数分後、火を止めてホイルを開くと、湯気と一緒に芳醇な香りがふわりと立ちのぼった。
皮がわずかに焦げ目を帯び、バターが金色に泡立っている。
箸を入れると、ほろっと身が崩れ、湯気が一瞬にして広がった。
「いただきます」
まずはムラソイから。
淡白な中にも深みのある身が、バターと塩の風味でさらに引き立っている。しっとりとした食感に、にんにくの香りが後から追いかけてくる。
カサゴは、さらに繊細だ。
やわらかくてふっくら、舌の上でほどけるように溶ける。脂がホイルの中で回っていたせいか、どこを食べてもじんわりと旨味が広がる。
口に入れるたび、思わず目を閉じたくなるような幸福感。
「……これは正解すぎたな」
冷たい風の中で釣った魚が、こんなにも温かい一皿に変わる。
あの瞬間、竿先がググッとしなったときの感触が、じわりと蘇る。
風はまだ冷たい。
けれど、今は部屋の中にいて、目の前には熱々の塩バター焼き。
釣れた魚を食べることが目的じゃない。
海と向き合い、魚と出会い、その命をいただき、自分の手で一皿に仕上げる──それが、僕にとっての釣りだ。
最後のひと口を口に運ぶ。
塩とバターの余韻を舌に残しながら、そっと息を吐いた。
「さあ、次はどんな魚に出会えるかな」

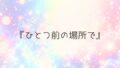

※コメントは最大500文字、10回まで送信できます