
夜の車窓に、景色が流れていく。
まるで、自分の記憶だけを運んでいくみたいだった。
川沿いを滑る光の帯。水面に映る街灯の明かりは途切れ途切れで、少し夢のなかみたいに現実感が薄れていく。
静かだった。車内には数人しか乗っていない。私は座席の隅に身を預けて、窓の外に視線を預ける。
どこかへ行きたかったわけじゃない。
でも、どこかへ向かわずにはいられなかった。
誰かの声に呼ばれた気がして、この時間の電車に乗っていた。
思い出すのは、やっぱり、あの日のことだった。
*
冬の入り口の夕方。駅の改札の前で、彼と立ち尽くしていた。
「……なんで、急に?」
どちらが言ったのかも、もう定かじゃない。最後のやりとりは、思っていたより曖昧だった。
彼の手はポケットに沈んでいて、目は私の奥を見ていた。
「ごめん」
それだけを残して、彼は電車に乗った。
私は残った。
別れよう、なんて言葉はなかったのに、すべてが別れのかたちをしていた。
扉が閉まり、電車が動き出す。
私たちは、それきりだった。
*
季節がいくつか過ぎて、ある日ふと思い出した。
あの駅、あの時間、あの場所。
いてもたってもいられなくなって、私は電車に乗っていた。
意味があるのかはわからない。でも、確かめたかった。
言えなかった言葉も、飲み込んだ感情も、まだどこかに残っている気がしていたから。
電車の揺れが、記憶を揺らす。
静かに、胸の奥に波紋が広がっていく。
ねえ、今どこにいるの?
なにしてるの?
もちろん返事なんてないけれど、それでも構わなかった。
思い出せるってことだけで、どこかでまだ繋がっている気がしていた。
あの頃、ふたりで乗った電車。
手をつながなくても、近くに感じられた距離。
いま、私はその場所へ向かっている。
ホームに降りた瞬間、胸の奥が少しだけ震えた。
懐かしい風景は、変わったようで、なにも変わっていなかった。
ベンチに腰を下ろして、スマホの画面を開く。
通知はひとつも来ていない。
私は電源を落とした。
今日は誰ともつながらなくていい。
ただ、電車と記憶と、自分だけでいい気がした。
ここに来たところで、彼に会えるわけじゃない。
わかってる。なのに、足は勝手にここまで来てしまった。
──「一緒に帰ろっか」
ふいに、耳の奥にあの声がよみがえる。
少し笑って、どこか照れくさそうで、それでもまっすぐだった。
記憶って不思議だ。
最後にどんな言葉を交わしたのかは思い出せないのに、どうでもいい一瞬の仕草や声だけが鮮明に残っている。
私は、彼に最後になにを言ったんだっけ。
言えなかっただけかもしれない。
黙ったまま、なにも返せなかったのかもしれない。
電車がホームに滑り込んできた。
わかってる。来るはずなんてない。
なのに私は、目で探してしまう。
似た背中を見つけるたびに、一瞬だけ期待してしまう。
でも違った。やっぱり、違った。
電車は扉を閉じて、ゆっくりと走り去っていく。
取り残されたホームに、ひとり。
私は、もう一度深く息を吐いた。
私が彼を思い出すように、彼もふと、私を思い出す瞬間があるんだろうか。
消せずにいるトーク履歴。
最後に送った「元気でね」という一文。
既読がついたまま、返事はなかった。
あのとき、それで全部が終わった気がした。
でも、もしも。
もしも、彼がまだあの言葉を覚えていてくれるなら。
それだけで、少しだけ前を向ける気がする。
ホームの風が少し冷たくなってきた。
もう少しだけ、この場所にいたいと思った。
彼を待っているんじゃない。
ちゃんと、自分と向き合うために。
そして私は、次の電車に乗ろうと思った。
終点まで、記憶を乗せて。
彼と降りたことのない駅まで、心を運んでみたかった。
窓の外は、相変わらず灰色の空。
でも、不思議と景色が違って見えた。
何度も通ったはずの道なのに、今日はどこか輪郭がにじんでいる。
車内の揺れに身を預けながら、私は膝の上で手を組んで、ぼんやりと外を眺めていた。
――あの日も、たしか、雨だった。
最後に彼を見た日。
私の前で立ち尽くしていた彼の姿だけが、時間に滲まず残っている。
「またな」
彼はそう言って、電車に乗った。
扉が閉まる直前まで、私を見ていた。
でも、私はなにも言えなかった。
手を振ることも、笑うこともできなかった。
見送ることしかできなかった自分を、いまでも時々、悔しく思う。
車内には、静かな空気だけが流れている。
イヤホンはしていないのに、頭の中にはあの頃の音楽が流れていた。
あの人の言葉、どれだけちゃんと受け取れていたんだろう。
そばにいれば、それでいいと思っていた。
言葉にしなくても、通じるものがあると信じてた。
だけど、そんなのはただの幻想だったのかもしれない。
名前を知らない駅が、いくつも通り過ぎていく。
降りたことのない場所でも、彼と話したことを思い出してしまう。
「このへんに、うまいラーメン屋があるらしいよ」
そんな話を、車内でしていた。
行くことはなかったのに、なんだかずっと覚えている。
私の記憶は、彼の言葉でできているのかもしれない。
特別じゃなくていい。
でも、忘れられない。
そんな時間ばかりが、今も胸の中に残っている。
過去に縋っているわけじゃない。
だけど、過去を手放す準備も、まだできていなかった。
彼がいなくなった日から、私の中に彼が根を張ってしまったから。
窓に映る自分の姿は、少しだけ大人びて見えた。
こうして静かに彼を思い出せるようになるなんて、あの頃の私は想像もしなかった。
あのときは、すべてが終わってしまったような気がしてた。
でも、時間は思っていたよりもやさしくて、
痛みを、すこしずつ滲ませていってくれる。
もしまた会えたら、私はなにを言うだろう。
「ひさしぶり」って、言えるかな。
それともまた、言葉が詰まって、目をそらしてしまうんだろうか。
きっと、もう会うことはない。
だからこそ、彼の姿はずっとあのときのまま、記憶の中に立ち止まっている。
電車は進んでいく。
もう戻れないことも、わかってる。
でも、記憶の中だけでも、彼と同じ景色を見ていたくて、
私はまだ、この列車の中にいた。
次の駅で降りるつもりだったのに、私はまだ座席にいた。
扉が開いても、体は動かなかった。
静かな車内。
どこか取り残されたような気がしたのに、不思議とその感じが心地よかった。
誰にも見つからない時間と場所。
その中にいることで、ようやく自分の輪郭がはっきりしていく。
あの人を思い出すとき、いつも風景の中に姿がある。
駅のホーム、電車の窓、雨の中の傘。
どこにもいないのに、確かにそこにいるような気がしてしまう。
いま彼がどこで、誰と、なにをしてるのかは知らない。
でも私は、彼との時間の中でしか、彼を探せない。
それでいい。
そう思えるようになってきた気がする。
かつて交わした言葉のほとんどは、もう思い出せない。
でも、声のトーンや、沈黙の間。
ふとした笑い方だけは、ずっと残ってる。
記憶って、不思議な場所を覚えてくれる。
形あるものじゃなくて、空気みたいなものだけを、ちゃんと拾ってくれる。
名前も、写真も、メッセージもいらない。
残しておきたいのは、
ただ、彼と一緒にいたときに流れていた時間だった。
缶コーヒーのぬるさとか、
改札の音とか、意味のない会話の続きとか。
そういう何でもないものが、今もちゃんと残っている。
窓の外。
知らない駅のホームで、誰かが誰かを迎えていた。
その光景が、少しだけまぶしく見えた。
私は誰にも会いにいくわけじゃない。
会える相手も、もういない。
ただ、記憶の続きを確かめたくて、こうして列車に乗っているだけ。
きっと、いつかはこの気持ちも過去になる。
だけど、今はまだここに置いておきたい。
「……またな」
最後に聞いた言葉が、ふいに頭の中で揺れる。
私も、返せなかった。
なにも言えず、ただ立ち尽くしていた。
あのときの自分に、声をかけたい。
でも、もうどうにもならない。
せめて、いまこうして思い出せていることが、
私なりの返事になればいい。
終点が近づいてきた。
車内アナウンスが、現実に戻るように響く。
降りなきゃ。
でも、降りたくなかった。
そんな気持ちを胸の奥で噛みしめながら、私はゆっくり立ち上がる。
扉が開いて、冷たい風が吹き込む。
外の世界に触れた瞬間、さっきまでそばにあった記憶が、少しだけ遠のいた。
でも大丈夫。
私の中に、ちゃんと残っている。
彼の言葉も、笑い顔も、何も言わなかった沈黙までも。
この列車の窓の向こうに、すべてを置いてきたようで、ほんとはずっと、自分の中にあった。
改札を抜けて、空を見上げる。
雨は止んでいた。
いま、私はようやく歩き出せた気がする。
何かが終わったんじゃなくて、何かを持ったまま、前に進めそうな気がした。
彼のことは、もう過去なのかもしれない。
だけど、完全に終わりにしたくないって思った。
たとえ誰にも語られることがなくても、誰とも共有できなくても。
それでも、私の中ではちゃんと、あの時間が生きている。
駅前のベンチに腰かけて、スマホを取り出す。
画面には、何も通知はなかった。
でも、不思議とそれでよかった。
思い出は、返事をくれない。
でも、いつもそばにある。
私はその日、ゆっくりと深呼吸して、帰りの電車に乗った。
もう、彼のいない風景にも慣れてきたけど、
それでも、どこかで今も彼を探してしまう自分がいる。
その気持ちは、もう否定しない。
記憶に残る彼の姿を、これからも私はきっと、忘れないでいる。
たとえ触れられなくても、もう会えなくても――
この胸に、静かに息づいているあの人との物語。
それだけはずっと、ここに置いておこうと思った。


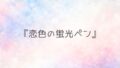
※コメントは最大500文字、10回まで送信できます