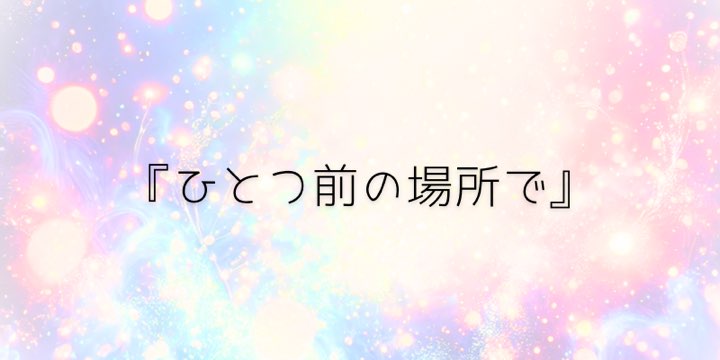
いつからだったか、私は“ひとりの場所”にいることが多くなっていた。
教室の端。誰も使わない席の隣。
昼休みの図書室。廊下に面した窓際の階段。
そこにいると、誰にも話しかけられないし、私も誰とも目を合わせずに済んだ。
「自分から輪に入ればいい」なんて――そんなに簡単な話じゃなかった。
誰かと話していても、心のどこかで“浮いてる”のを自覚してた。
声のトーン、話題のセンス、反応の速さ。
どれも、うまく馴染めない。
でも、それでもいいと思っていた。
無理して合わせるよりは、ひとりでいたほうが楽だったから。
そんな日々の中、
――彼は、何の前触れもなく声をかけてきた。
「その本、おもしろい?」
振り返ると、クラスの男子が立っていた。
名前は、陽斗(はると)くん。
特別目立つタイプでもないけど、どこか落ち着いてて、
授業中もいつも静かにノートを取っている人。
「え、あ……うん。まあ、普通かな」
思わず声が裏返る。
彼は、にこっと笑って、
「そういう“普通”って実は一番面白かったりするよね」
って言った。
なんだそれ、って笑いそうになったけど、うまく笑えなかった。
「……そうだね」
小さくうなずいた私に、それ以上なにも言わずに、彼は隣の席に腰を下ろして、自分の本を開いた。
それだけだった。
でも、私はその日、心の中で何度もあの言葉を反芻してた。
“その本、おもしろい?”
それは、誰からも向けられなかった言葉だった。
次の日も、図書室の窓際に座っていると、
彼がふらっと現れて「また会ったね」と笑った。
それからのことは、よく覚えていない。
気づけば、毎週のようにそこで顔を合わせていたし、彼が座ることも、話しかけてくれることも、当たり前みたいに感じるようになっていた。
でも、本当は当たり前じゃない。
あの教室で、私にまっすぐ声をかけてくれたのは、彼だけだった。
最初に気づいたのは、隣の席の子のほんのわずかな視線だった。
授業が終わって、プリントを回すとき。
一瞬、目が合って、それからそらされる。
そのあと、友達と何かをひそひそと話している。
たぶん、彼と図書室で話してるのを見られたんだ。
別に悪いことをしてるわけじゃない。
でも、そんなふうに見られるのは、やっぱり少し怖かった。
「……噂になってるかも」
放課後、いつもの図書室の席で、彼が言った。
「えっ……やっぱり?」
私は思わず声をひそめた。
「まあ、目立つよね…ふたりでいるの、毎回同じ場所だし」
彼はそう言って、本を閉じた。
私はうつむいたまま、何も言えなかった。
「嫌だった?」
静かな声が降ってくる。
「……ううん」
本当は、少しだけうれしかった。
誰かと一緒にいることで、誰かに見られること。
彼と並んでいる自分を、誰かが気にしているという事実。
そんな小さな出来事が、自分を“存在している”と思わせてくれた。
だけどそれを、正直に口にする勇気はなかった。
「……でも、もう話さないほうがいいかも」
ぽつりと、私が言った。
彼は少しだけ黙って、それから、
「じゃあ、人前じゃ話さない。放課後だけね」
と微笑んだ。
その笑顔に、なぜだか涙が出そうになった。
それからの私たちは、図書室ではなく、校舎裏のフェンス沿いや、帰り道の途中の公園。
お互いのスマホに送る短いメッセージ――
人目につかない場所で、少しずつ言葉を交わし
ていった。
誰にも知られない関係。
でも、それは私にとって、確かに“特別なも
の”になっていった。
目が合えば少し微笑むようになった。
名前を呼ばれるだけで、なんだか安心するよう
になった。
気づけば、季節は春の終わりを迎えていた。
そんなある日――
部活の先輩に呼び出された。
放課後の体育館裏。誰もいない静かな場所で、
「前から気になってたんだ」って、先輩はまっすぐ言った。
何が起きてるのかわからなくて、ただ黙ってうなずいた。
断ったわけでも、受け入れたわけでもなかった。
でも“誰かに好かれた”という事実だけが、胸の中で大きくふくらんでいった。
帰り道、スマホを握りしめて歩いていた。
なんとなく、彼に伝えたくなって、メッセージを打っていた。
『……さっき、先輩に告白された』
少し間が空いてから、既読がついた。
そして、返ってきたメッセージはたった一行。
『……そっか。でも、できれば付き合ってほしくないかな』
画面を見つめて、数秒間止まった。
何それ。
すぐには意味がつかめなかった。
けど、彼が冗談みたいにそう言うのが、なんとなく目に浮かんだ。
『……なんで?』
『いや、なんとなくだけど』
それだけの会話。
でも、私はほんの少し、拍子抜けした。
彼なら、いつものように「よかったね」って、
優しく背中を押してくれると思っていたから。
『応援してくれると思ったのに』
打ったあと、すぐに後悔した。
ちょっと意地みたいになっていた。
返ってきた言葉は、それでも優しかった。
『ごめん』
たったそれだけ。
でも、なんとなくそれ以上は続けられなかった。
スマホを閉じて、息を吐く。
浮かれていたんだと思う。
“誰かに選ばれた”ことに、
期待してしまった自分が恥ずかしかった。
陽斗くんは、先輩の噂を知っていたのかもしれない。
それを言わずに、ただ「付き合ってほしくない」と笑った。
私だって、少しは聞いたことがあった。
でも、“そんなはずない”って、思いたかった。
彼の静かな優しさを、
私はきっと――見えなくなっていた。
その数日後、噂はあっさりと現実になった。
告白してきた先輩が、他の子にも声をかけていたこと。
わたしのことを「ちょっと押したらすぐいけそうだった」って話していたこと。
中途半端な期待を持った自分が、
何より一番、恥ずかしかった。
誰にも言えなくて、ただ静かに、
自分の中にその感情を押し込めた。
あの日、彼の言葉を信じていたら。
「付き合ってほしくない」なんて、そんな遠回しなやさしさじゃなくて、はっきり伝えてくれたら。
……いや、ちがう。
見ようとしなかったのは、わたしの方だった。
自分に都合のいい方だけを見て、優しさは、面倒くさいものに思えて、気づかないふりをしていた。
――放課後。
昇降口の前、帰る準備をしていたとき。
ふと目が合った彼が、ゆっくり近づいてきた。
「……大丈夫?」
たったそれだけのひと言。
でも、その声を聞いた瞬間、
涙が一気にあふれて、止まらなくなった。
人がいる場所だったのに、そんなこと気にしていられなかった。
恥ずかしくても、かっこ悪くても、もう全部どうでもよかった。
彼は何も言わなかった。
ただ、横にいてくれた。
何も詰めないで、何も責めないで、
そのままのわたしを、受け止めてくれた。
ずっと、優しかった。
ずっと、変わらなかった。
わたしが勝手に浮かれて、見えなくなっていただけだった。
その日、家に帰って布団の中で、
わたしは小さく声に出してみた。
「……陽斗くん」
名前を呼んだだけなのに、
胸の奥が、じわりとあたたかくなった。
もっとずっと前から、私は彼のことが好きだった。
あのとき、ちゃんと気づいていればよかった。
ちゃんと伝えていれば、こんなに遠回りしなかったのに。
――夕方の風が、制服の裾を軽く揺らした。
校舎裏のフェンスの前。
わたしたちは、並んで座っていた。
「……ごめんね、あのとき」
ぽつりと、わたしが言った。
陽斗くんは、少しだけ驚いたように顔を向ける。
でも何も言わず、視線を空に戻した。
「ちゃんと、見えてなかった。自分のことでいっぱいいっぱいで……」
こんなふうに素直に言えるのに、どれだけ時間がかかっただろう。
彼は静かに言った。
「俺は、全然大丈夫だよ」
ああ、やっぱり。
いつだって、自分のことよりわたしのことを先に気にしてくれる。
だから、わたしは。
「……ねえ」
声が少しだけ震える。
「わたしのこと、好きになってくれる?」
言葉にした瞬間、胸がぎゅっと締めつけられた。
ずうずうしいってわかってた。
勝手すぎるってわかってた。
でも、それでも――どうしても聞きたかった。
陽斗くんは、しばらく何も言わなかった。
やがて、ゆっくりと口を開いた。
「……それは、無理だよ」
――当然の言葉だった。
あのとき、わたしは彼の優しさを遠ざけた。
見なかったふりをして、向き合おうともしなかったくせに。
ひどいのはわたしなのに、なんでこんなに苦しいんだろう。
涙がこぼれた。
頬を伝って、制服に落ちる。
「……ごめん、変なこと言って」
声がうわずって、自分でも何を言っているのか分からなかった。
そのとき、彼がわたしの手を、そっと握った。
「っ……」
目を見開く。
あたたかくて、ちゃんと力があった。
「ごめん。ちょっと、いじわるだった」
彼は、照れたように笑う。
「でも――もう一度“好きじゃなかった頃”に戻るのは、無理だから」
わけがわからなくて、なのに、
胸の奥が、溶けていくようにあたたかくなった。
「……なにそれ」
笑ってるのか泣いてるのか、自分でもわからなかった。
でも彼は、そんなわたしを見て、優しく笑った。
――変わらないその笑顔が、
わたしのすべてを、そっとほどいてくれた気がした。
またここから始められる。
今度は、ちゃんと隣で笑えるように――

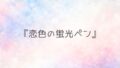

※コメントは最大500文字、10回まで送信できます