
「……可愛いいよね?」
そんな友達の言葉に、曖昧に笑って「まぁ、可愛いよな」なんて合わせておいた。
話題にあがっていたのは、隣のクラスの女子だった。
特別目立つタイプじゃない。でも、密かに思ってる男子は多い。自分も、その中の一人だった。
彼女は吹奏楽部で、仲のいい女子グループと男子グループがあって、休みの日はよく一緒に遊んでるらしい。そういう話を聞くたび、ちょっとだけ胸がざわついた。
話しかけたことなんてほとんどないのに、気づけば目で追っている。教室の窓から見える廊下、昼休みの移動中、たまたま近くを通り過ぎるとき。なぜか気になる存在だった。
だから、その日もたまたまの出来事だったはずなのに、やけに心臓が跳ねた。
休み時間。ノートをまとめていたとき、ふいに声がした。
「そのペン、かわいいね」
顔を上げると、彼女が立っていた。
思わず一瞬、言葉が出なかった。
「……ああ、これ? 修学旅行のときに買ったやつ」
キャラクターの顔が並んでいる5色の蛍光ペン。ちょっとした遊び心で買ったものだったけど、まさかこんなふうに話題になるとは思っていなかった。
「使ってみていい?」
「いいよ」
手を伸ばしてきた彼女の肩が、ほんの一瞬だけ自分の腕に触れた。
「……あっ、ごめん!」
思わず彼女のほうを見ると、照れたように笑って、ペンを手に取っていた。
「……いいね、これ。黄色とか、目立つし」
「使う?」
「いいのー? じゃあ借りようかな」
ニコッと笑った顔に、どこか子どもみたいな無邪気さがあって、その瞬間だけ教室の音がすっと遠のいた気がした。
たったそれだけのこと。でも、ずっと心に残った。
***
それから、彼女が時々ペンを借りにくるようになった。
「今日も黄色、借りていい?」
「どうぞ」
「ありがと!」
そんな他愛ないやり取りが、だんだんと自然になっていく。
何か特別なことを話すわけじゃない。でも、ペンを渡すときに少しだけ指が触れたり、彼女の視線がちらっと合ったり。些細なことが、いちいち胸をくすぐった。
渡した黄色のペンで、彼女が楽しそうにノートを書いてる姿を、隣の教室のガラス越しに見るのが、ひそかな楽しみになっていた。
彼女はそれを知らない。
でも、自分にとっては、たったそれだけのやり取りが、ちょっとずつ、確かに、特別になっていた。
ある日のこと。
教室でノートを整理していると、彼女と同じ吹奏楽部の子がひょいと顔を出してきた。
「ねえ、ペン貸してあげてるんだって? やさしいじゃん〜」
からかうような笑い声と一緒に、意味ありげな視線を向けてくる。
「なんでわざわざ、隣の教室まで借りに来るんだろうね〜?」
その言葉が、妙に心に引っかかった。
昼休み。
彼女は来なかった。
誰かに見られてる気がして、ドアの方を見るたび、つい期待してしまう。
けれど、誰も来ない。
机の上には、いつも通りに用意していたキャラペンだけが並んでいた。
——来ないだけで、こんなに静かに感じるのか。
その日の夜。
スマホに通知が届いた。
フォローも何もされていないアカウント。けれど、プロフィールの一言とアイコンの雰囲気で、すぐに彼女だと気づいた。
「なんか変な噂されちゃってて…ごめんね」
「変な噂って?」
「2人っていい感じだよね、みたいな…」
「それだけ?」
「うん。」
「そんなの全然気にしないよ。むしろ、そう思われてるの、ちょっと嬉しいけどな」
「なにそれ、変なこと言わないでよ笑」
打ち明けてくれたことが、ただ嬉しかった。
ふたりの距離が、少しだけ近づいたように感じた。
数日後。
彼女が吹奏楽部の友達と一緒に、また教室に来た。
「最近、優しくしてもらえなかったんじゃないの〜?笑」
いつものように茶化されている彼女が、こちらをちらりと見て、照れたように小さく言う。
「……ごめん。また、借りてもいい?」
「もちろん」
「私も借りようかな〜」と横から友達。
「ごめん、好きな子にしか貸さないことにしてるんだよね」
「なにそれ〜! 特別扱い〜?」
「あっ…ごめん、知らなかったから…」
彼女は申し訳なさそうに目を伏せて、指先でキャラペンの端をそっとつまんだ。
「いや、だからずっと貸してたんだけど」
そう言って、笑いながら返すと——
彼女は一瞬きょとんとして、何か言いかけたけれど、小さくうなずいてペンを持ち上げる。
「……ありがとう」
そう言って、顔を赤らめながら足早に教室を出ていった。
「……えっ? ちょっと待ってよ〜!」
置いていかれた吹奏楽部の友人が、慌てて後を追いかけていく。
——ちょっと、言いすぎたかな。
そう思いながらも、胸の奥では小さな期待が膨らんでいた。
その夜、彼女からのメッセージ。
「今日もありがとう。また借りにいくね」
「いつでもどうぞ」
少し間があって、ポンと通知がまた鳴る。
「あのさ、お昼の話って……」
「ん?」
「好きな子にしか貸さないって……」
「あれは冗談だよ笑」
「びっくりした〜」
「ごめんね!でも、この先きっと好きになると思う」
「その冗談は返事に困るよ〜」
「これは冗談じゃないよ」
「もう、なにそれ笑…そういうのは、普通は心の中に閉まっておくものじゃないの?」
「え? もしかしてはみ出してた?」
「はみ出してる!」
「じゃあ、もう好きってことかもしれないな、ちゃんと隠しておこう!」
「隠す気ないじゃん笑、全部言ってる!」
「秘密にしておいてくれない?笑」
「もう……明日からどんな顔して会えばいいの…」
「じゃあ、おやすみ」
「寝れないじゃん…おやすみ!」
翌日。
休み時間になると、彼女はまたそっと教室に現れた。
少し髪を耳にかけるしぐさ。笑ってはいるけど、どこか緊張しているように見えた。
「今日も……借りていい?」
「もちろん」
手を伸ばしながら、彼女がぽつりと呟く。
「昨日のメッセージ…」
「……あ、ごめん!好きってこと、秘密にしておいて!お願い!」
「もう……!」
照れたように目をそらす彼女を見ながら、心がじんわりと熱を帯びていくのがわかった。
それから、ふたりのやりとりは日常になった。
「ねぇねぇ、また借りに来たの〜?笑」
「うるさいなぁ!」
吹奏楽部の友達がからかっても、彼女はもう、逃げるような顔はしなかった。
ちらりとこちらを見て、困ったように笑って、それから——小さく、嬉しそうに笑った。
放課後。
机の上。黄色のペンの横に、ひとつの小さなメモが添えられていた。
『明日は……赤色もお願い』
丸く優しい文字と、うさぎとも猫ともつかないゆるキャラの落書き。
それを見て、思わず笑ってしまった。
明日も、また彼女と話せる。
たったそれだけの確信が、今日一日の終わりを、そっとあたたかく包んでくれた。


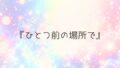
※コメントは最大500文字、10回まで送信できます